
paizaでは、エンジニア組織のリーダーやそれを目指す方々のためのメディア「Tech Team Journal」を公開しています。
今回は、企業のCTOに対談していただく連載企画「Tech Career Talk」の記事をご紹介します。
本連載では、第一線でご活躍されているエンジニア組織のリーダーをお招きして、対談形式でこれまでのキャリアや組織のリーダーとして大切にしていること、組織課題などを語っていただいています。
ナビゲーターは元DMM.com CTOで、現在は株式会社デジタルハーツでCTOを務める城倉和孝氏です。
それぞれに課題や乗り越え方など特徴がある一方、企業規模や事業領域は異なるものの、組織のリーダーとして皆さんが共通して持っている考え方というのも見えてきました。
Vol.1 株式会社OKAN CTO・川口登氏
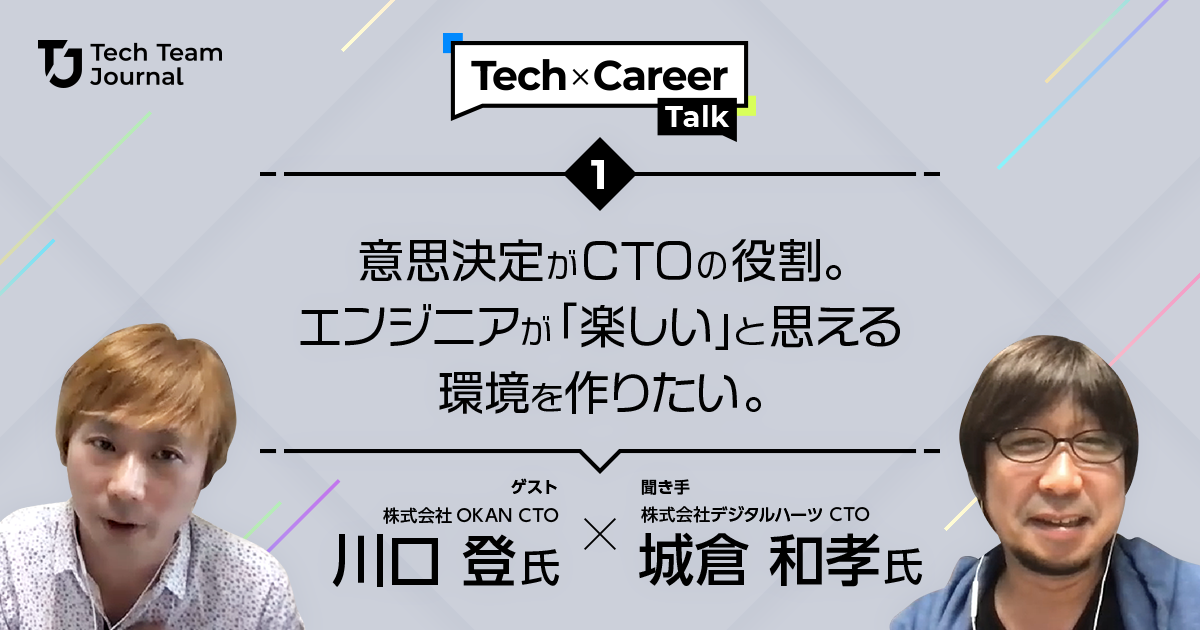
意思決定がCTOの役割。エンジニアが「楽しい」と思える環境を作りたい。
福利厚生として人気の高い、健康的でおいしいお惣菜を全国のオフィスや従業員の自宅に届けてくれる置き型社食®︎サービス「オフィスおかん」を提供する株式会社OKAN。
川口氏は「『お惣菜』は課題解決のためのひとつのツール」と捉え、CTOとして入社後は、補助的だったITの役割を事業をドライブさせるために必要不可欠だと考え、エンジニアの組織づくりを推進し始めました。
技術選定ではエンジニアが興味を持てるかという視点も重要だとし、サービスとしての永続性や技術の流行り廃りも見極めながら「楽しめる」を大切にされていることが伝わってきます。
対談から一部抜粋:
城倉:経営に寄り添って変化をしていくというのと同時に、エンジニアの幸福度をとても大事にされてると思うんですけど、それらを両立していくにあたってCTOとして気をつけられていることってありますか?
川口:これは難しい問いですね。これまで私が意思決定して決めちゃうという話をいくつもしたと思うんですけど、本当は何も言わなくても動ける状態が望ましいなとは思ってるんです。
なので私がいなくてもよくなって、エンジニアが主体的・自律的に動ける組織になると幸福度が高い状態に近いのかなと考えています。
Vol.2 株式会社モバイルファクトリー エンジニア組織開発責任者・小林謙太氏

エンジニアに成長機会+働きやすさを提供したい。そのための仕組みを整えるのがリーダーの役割
位置ゲームをはじめとしたソーシャルアプリや、モバイルコンテンツサービス、ブロックチェーン事業などを開発・運営する株式会社モバイルファクトリー。「エンジニア組織開発責任者」ということで、役割としてはVPoEに近く、エンジニア組織の責任者として開発の生産性を上げることにコミットしている小林氏。
新卒で同社に入社しエンジニアとしてコードを書くことが好きだと感じながらも、自らマネジメントをやってみたいと手を挙げたと言います。
エンジニアが自己成長できる環境づくりが組織的な課題だと捉え、どのような取り組みをおこなっているか、また難しいと感じている点についても語っていただきました。
対談から一部抜粋:
城倉:小林さんがエンジニア組織の責任者として一番大切だと考えていることは何ですか。
小林:基本は楽観的であるといいなと思っています。
もちろん悲観的な考えも使うんです。開発ではその人間の能力を過信しないで、それこそ仕組みに頼るとか、「事故は起きるものだ」と思っているとか、そういうところは悲観的に考えることもあります。でも人と接していく部分は楽観的であったほうがいいと思うんですよね。
城倉:仕組みは悲観ドリブンで、実施は楽観的にってことですか。
小林:そうかもしれないですね。新型コロナウイルスもそうですけど、経験したことがないような問題とかに向き合わなきゃいけない場面もあるじゃないですか。でもそこでバタバタするんじゃなくて、「急に来たね、逆風」くらいの気持ちで受け止められないといけないなと。
Vol.3 セーフィー株式会社 取締役 開発本部長 兼 CTO・森本数馬氏
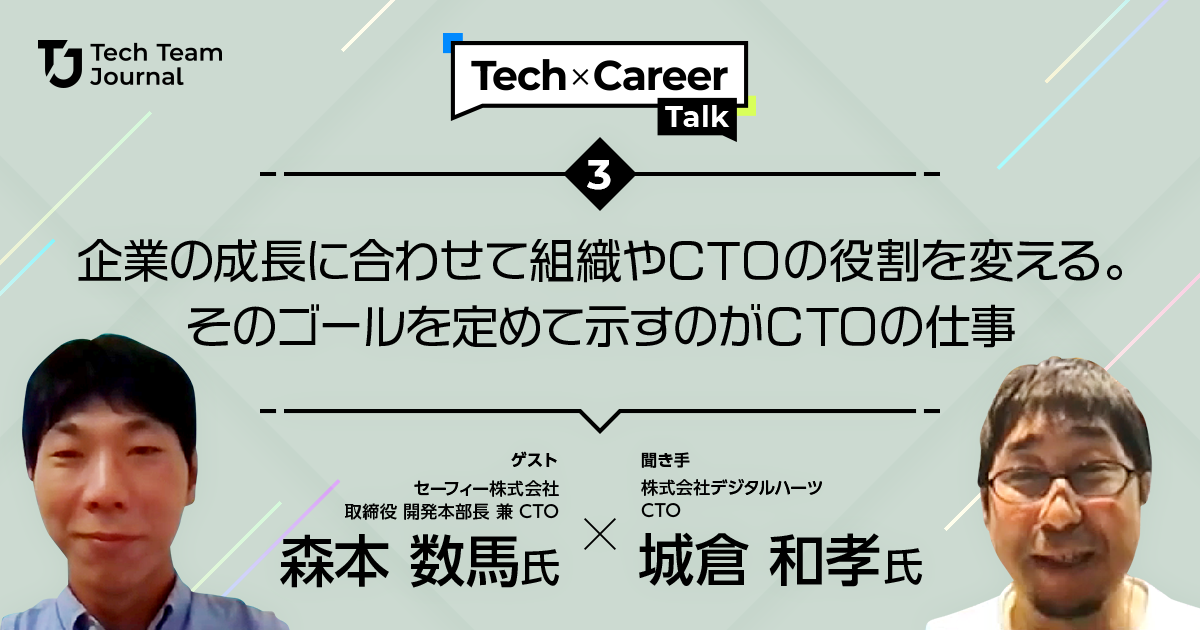
企業の成長に合わせて組織やCTOの役割を変える。そのゴールを定めて示すのがCTOの仕事
カメラとインターネットをつなぐだけで、いつでもどこでも映像を確認できるクラウド録画サービスの開発事業を手がけるセーフィー株式会社。
同社の創業メンバーでもある森本氏は、現在はCTOとして組織のロードマップや技術戦略の策定、進捗の管理、そしてそれらに合わせた組織づくりや採用活動に取り組んでいます。
組織が大きくなる中で目的を大切にし、仕事の楽しさも忘れずにいるために重要なことは何かもお話しいただきました。
対談から一部抜粋:
城倉:CTOにとって大事な要素についてはどうお考えかをお伺いできますか。
森本:個人に対しても組織に対しても、ゴールを明確に設置して、それについてきちんと説明した上で、達成のためのアクションが実施できることだと思います。自分で言うと、できている部分も多少はありますが、まだまだ全然足りていないと感じています。
城倉:なるほど。そのCTO像に近づくために努力されていることや、気をつけていることは何かありますか。
森本:「どこを目指しているか」を説明するということは、ひたすらやっているところですね。CTOとして、きちんと説明をして、組織としての方向性を示す。最初はふわっとしたまま進めてしまうこともありましたが、そういった進め方はおこなわないよう心がけるようにしています。
Vol.4 株式会社Save Medical CTO・川上知成氏

デジタル治療アプリ開発への挑戦。CTOとして開発チームを一から作り上げるために奮闘中
ソフトウェアを利用して治療する「デジタル治療(DTx)」の開発を手がける株式会社Save Medical。ヘルスケアスタートアップとして医療領域でさまざまなチャレンジをおこなっています。
同社CTOの川上氏は、ジョインして約半年(2021年8月取材時点)でスピード感を持って開発チームをリードしてきました。
「たくさんの人を喜ばせることがモチベーションにつながる」と話し、ITの力で解決できる課題がまだまだあると熱く語ってくださいました。
対談から一部抜粋:
城倉:川上さん自身がこの事業をスケールさせたいと感じるモチベーションや面白みって、どこにあるんでしょうか。
川上:この治療用アプリが実現されると、ドクターや糖尿病療養指導士さんが患者さんと直接会えなくても、一定の効果を見込めるような治療が提供できると想定しています。将来的に医療従事者のスキルがアプリ上で再現できれば、それによって救われる方がたくさん出てくるはずです。
患者さんの病状がよくなるのはもちろん、医療従事者の方々の負荷が減れば、より人の手が必要な治療に時間を使えるようになりますから、結果としてさらにたくさんの人を喜ばせることができると思っています。そういった意義が自分のモチベーションになっていますね。
他にもさまざまなテーマの記事を公開中!
TTJ お悩み相談室
エンジニア組織や採用のお悩みをプロが解決する人気コーナー。アドバイザーは、UUUM株式会社の元CTOで、現在Repro株式会社の執行役員CTOを務める尾藤正人氏です。
お悩み:CTOを目指すエンジニアは20~30代をどう過ごすべきか
お悩み:エンジニアの評価方法を改善したい
リーダーインタビュー
数々の経験・事例を持つトップランナーたちからお話を伺い、「令和のITエンジニアに求められるスキルセット・マインドセット」「これからのIT社会で必要とされるエンジニアリング組織」について解き明かします。
Sansan株式会社 CTO・藤倉成太氏
藤倉成太氏に、Sansanにおけるエンジニアおよびエンジニアリング、その集合体としての組織のあり方についてお話を伺いました。そして、次の10年に向けた新しい組織像と実践についてのお話もお届けします。続きはこちら
GMOペパボ株式会社 CTO・栗林健太郎(あんちぽ)氏
あんちぽ氏は、自社のエンジニアチームを「コミュニティ」と捉え、チーム作りやプロダクト開発を進めています。GMOペパボのエンジニアリングを支えるものは何か? 今回のインタビューで核心に迫ります。続きはこちら
「paizaラーニング」では、未経験者でもブラウザさえあれば、今すぐプログラミングの基礎が動画で学べるレッスンを多数公開しております。
詳しくはこちら

そしてpaizaでは、Webサービス開発企業などで求められるコーディング力や、テストケースを想定する力などが問われるプログラミングスキルチェック問題も提供しています。
スキルチェックに挑戦した人は、その結果によってS・A・B・C・D・Eの6段階のランクを取得できます。必要なスキルランクを取得すれば、書類選考なしで企業の求人に応募することも可能です。「自分のプログラミングスキルを客観的に知りたい」「スキルを使って転職したい」という方は、ぜひチャレンジしてみてください。
詳しくはこちら





