
Photo by dee_dee_creamer
 こんにちは、谷口です。
こんにちは、谷口です。
ITエンジニアとして働いている皆さんは定期的に勉強をしていますか?
『How Google Works』という書籍では、「人材」の章で、常に勉強し続ける人たちのことを「ラーニング・アニマル」と呼び、Googleが採用したい人材であるとしています。
しかし、業務時間外にしろ時間内にしろ、何でエンジニアはこんなに常に勉強やスキルアップに関することを言われ続けないといけないのでしょうか。エンジニアは常に勉強を続けなければ生き残っていけない職業なのでしょうか。
今回は、エンジニアが勉強し続けることの必要性について考えていきたいと思います。

How Google Works (ハウ・グーグル・ワークス) ―私たちの働き方とマネジメント
- 作者: エリック・シュミット,ジョナサン・ローゼンバーグ,アラン・イーグル,ラリー・ペイジ,土方奈美
- 出版社/メーカー: 日本経済新聞出版社
- 発売日: 2014/10/09
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (18件) を見る
■『How Google Works』における「ラーニング・アニマル」
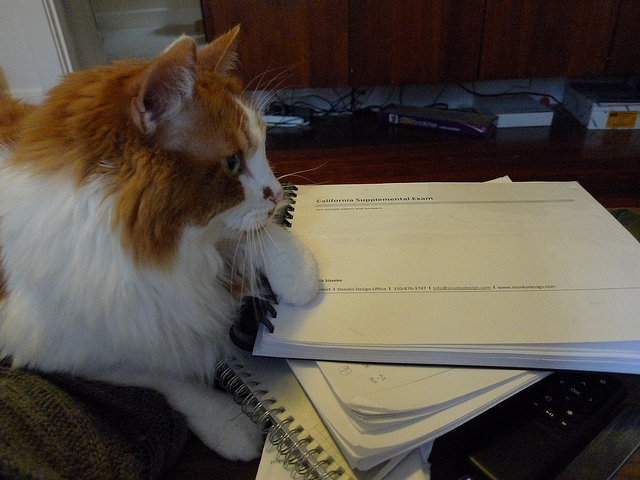
Photo by Mark Hogan
例えば企業でポストが一つあき、誰か新しい人材を採用しなければならなくなったとしましょう。ほとんどの採用活動では、過去に同じような仕事の経験があることを条件に人を選ぶかと思います。
しかし『How Google Works』では、あらゆる業界では急速な変化が起きており、一つのポストに関しても、求められるスキルや役割は変わっていくとした上で
グーグルが採用したいのは、ジェットコースターを選ぶタイプ、つまり学習を続ける人々だ。彼ら"ラーニング・アニマル"は大きな変化に立ち向かい、それを楽しむ力を持っている。
としています。
確かにIT技術の世界が常に変化のジェットコースターの中にある以上、多くのエンジニアにとって重要な仕事の一つは「変化に対応すること」なのではないでしょうか。
数年前には存在もしていなかったのに、今ではメジャーとなっているような開発言語やフレームワークも珍しくありません。そんな中で、普通に働くエンジニアのほとんどは「私は今までもこれからもこの言語のこのバージョンしか使いませんので」というわけにはいかず、必要に応じて新たな勉強をしてきたことと思います。
そう考えると、採用では「すでに習得済みなこと」だけではなく、「変化が起きたときに対応できるそうか」「未知のもの、新しいものに対しても意欲的であるか」が重視されるべきだと言えます。
■しなやかマインドとこちこちマインド
本著はさらに「ラーニング・アニマル」について、
心理学者のキャロル・ドゥエックは、これを別の言葉で表現する。「しなやかマインドセット」だ。
と続きます。
ドゥエック氏はスタンフォード大学で主に教育における心理学を研究している教授で、「マインドセット」とは「知能観」、ざっくり言うと「自分の能力についての考え方」とされています。
このマインドセットには、「しなやかマインドセット」と「こちこちマインドセット」があり、以下の考え方の傾向に分かれています。
【こちこちマインドセット】
・自分の能力は生まれつき決まっていて、努力をしても変わらない
・今ある能力で「できる」「できない」を判断する
・自分が失敗するところは見せたくない
・自分が他人からどう評価されるかを気にする
・結果を重視する
【しなやかマインドセット】
・自分の能力は努力次第で伸ばして変化させることができる
・今できないことでも、これから学べばできるようになる
・失敗したとしても次がある
・過程を重視する
ドゥエック氏は香港大学で、英語の苦手な学生に対して難易度の高い英語の授業を履修するかどうかを聞くと同時に、その学生がどちらのマインドセットを持っているかを判定する質問にもいくつか答えてもらうという調査を実施しました。
その結果、しなやかマインドセットに当たる学生は「自分の英語力をアップさせられそうだ」と感じて英語の授業を履修し、こちこちマインドセットの学生は「自分の英語力ではこの授業は理解できそうにないから履修したくない、低い実力をさらすのも恥ずかしい」と感じてあまり興味を示さなかったそうです。
初めてのことや難しい課題を目の前にしたとき、こちこち系の人は、失敗や他人からの評価を気にして「今の能力でできる範囲のことしかしないようにしよう」「わからないことがあるけど、こんなことを質問して馬鹿にされると嫌だから聞かないでおこう」となってしまいがちです。
対してしなやか系の人は、自分の能力は向上させられるという考えがあるため、「自分はここまでしかできない」というような制限を設けず、「今はわからないことがあっても、努力すればいずれできるようになる」という感じであまり迷わず挑戦する傾向にあります。
英語に限らず、どちらのマインドセットを持った人間の方が変化に適応し続けられるかということは明らかだと思います。
■必要なのは「いつでも勉強を始められるマインド」と「環境」

Photo by Michael
ITエンジニアが知的労働者である限り、商売道具である知を磨くことは歓迎されるべきですし、エンジニアというのは基本的には上記のようなしなやかマインドを有する人たちであるべきではないでしょうか。
同時にエンジニアを雇う側の企業も、「新しい開発環境なども導入していこう」「直接業務に関係のない勉強もサポートしよう」といった感じで、しなやかマインドにフィットした環境であるべきではないでしょうか。
企業側が「新技術?今までのままでいいだろう」「業務外学習はサポートしない」といった環境では、働く側も「じゃあ勉強しないでできる範囲だけのことやっておけばいいや…」という感じで、マインドもどんどんこちこち側に傾いてきてしまいます。
当然ながら、ほとんどの企業はそういった「できる範囲のことしかやりません」という人よりも、向上心のある人を求めているはずだと思いますが、そのためには職場もそれなりの環境に整えていく必要があります。
「本当にできる人はどんな環境でも放っておいても勉強できるだろう」と思うかもしれませんが、そういう人は「もっとよい環境があるな」と思ったらそっちに移動してしまいます。そして、一般的な普通の人は良くも悪くもある程度環境に左右されることが多いため、意識の低い環境にいるとつい流されてしまいがちです。
時間外とか時間内とか、業務外とか業務内とかいうことは関係なく、学びたいことができたらすぐに手を出せるような環境やマインドに、企業もエンジニア個人もフィットできているとよいのではないでしょうか。
■まとめ
ITエンジニアにとって「勉強が習慣になっている」ということは大きなスキルであり、選択の幅も広げることができます。そして大きな変化があっても振り落とされずに対応しながら生きていける、業界内でもサバイバル能力の高いエンジニアになれるのではないかと思います。
一生エンジニアとして生きていこうと考えている方は、まず自分のマインドをしなやかな方向に整えていくことから始めてみるとよいのではないでしょうか。

How Google Works (ハウ・グーグル・ワークス) ―私たちの働き方とマネジメント
- 作者: エリック・シュミット,ジョナサン・ローゼンバーグ,アラン・イーグル,ラリー・ペイジ,土方奈美
- 出版社/メーカー: 日本経済新聞出版社
- 発売日: 2014/10/09
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (18件) を見る

- 作者: キャロル・S・ドゥエック,今西康子
- 出版社/メーカー: 草思社
- 発売日: 2016/01/15
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (1件) を見る
paizaは、技術を追い続けることが仕事につながり、スキルのある人がきちんと評価される場を作ることで、日本のITエンジニアの地位向上を目指したいと考えています。
「paiza転職」は、自分のプログラミング力が他社で通用するか(こっそり)腕試しができる、IT/Webエンジニアのための転職サービスです。プログラミングスキルチェック(コーディングのテスト)を受けて、スコアが一定基準を超えれば、書類選考なしで複数の会社へ応募ができます。
まずはスキルチェックだけ、という使い方もできます。すぐには転職を考えていない方でも、自分のプログラミングスキルを客観的に知ることができますので、興味がある方はぜひ一度ご覧ください。
また、paiza転職をご利用いただいている企業の人事担当や、paiza転職を使って転職を成功した方々へのインタビューもございます。こちらもぜひチェックしてみてください。
詳しくはこちら




