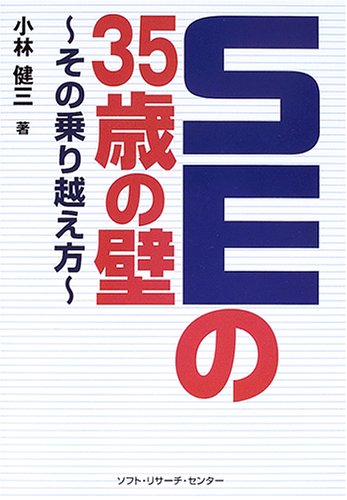IT業界で働くエンジニアのキャリアについて、以前は「35歳定年説」などという言葉がありました。ただ、最近では死語と言えるのではないでしょうか。
近年は30代、40代となってもエンジニアとして活躍されている方はめずらしくありません。30代以降から転職を目指すエンジニアも増えてきましたし、paizaの開発チームにも30代後半以上のエンジニアは何人も所属しています。
この記事では、そもそも「35歳定年説」がなぜ生まれたのか、その後IT業界の現状はどうなっているのかについて考えたいと思います。
歴史的背景:なぜ「35歳定年説」が生まれたのか
「35歳定年説」とは、簡単に言うとITエンジニアの現場でのキャリアは35歳前後で限界を迎えるという俗説です。明確な発祥源は不明ですが、IT業界の黎明期からすでにあったとも言われており、2000年代頃になると書籍などでもさかんに取り上げられるようになりました。実際に2005年には「エンジニア 35歳からの転職」「SEの35歳の壁」といった本が出版されるなど、広く通説として語られていたことがうかがえます。当時は「35歳で限界」という見方がなかば常識化していたと言えるでしょう。
この俗説が生まれた背景には、当時のIT業界特有の過酷な労働環境と画一的なキャリアパスが大きく影響しています。
当時IT系の就職先として一般的だったシステムインテグレーター(SIer)では、まず新卒一括採用で入社したエンジニアはプログラマとして現場の開発に没頭する。30代になるころにはSE(システムエンジニア)やプロジェクトリーダーへと昇格し、管理業務や上流工程へ移る。つまり35歳前後で開発の第一線からは離れるというキャリアパスが一般的でした。
この現場から離れるタイミングを誇張して「定年」と表現し始めたことが、35歳定年説の由来だと思われます。
業界の状況と「35歳限界」を生んだ要因
「35歳定年説」が浸透していった背景には、以下のような業界状況や労働環境の問題がありました。技術変化のスピードと陳腐化
IT技術の進歩は非常に速く、エンジニアは常に最新技術を習得し続けなければなりません。ときには長年培ったスキルを捨てて、新技術に乗り換える柔軟性も必要となるでしょう。
しかし一般に、学習意欲や順応力は年齢とともに低下すると思われています。
そのため「10年も経てば技術についていけなくなる」=「エンジニアが第一線で活躍できる寿命は10年程度(=30~35歳くらいまで)」という見方もあったのではないでしょうか。
年功序列による人件費高騰
日本の年功序列型の賃金制度では、年齢を重ねたプログラマほど給与が高くなります。そのため「プログラミングは新人にさせるべき単純作業」と考えているような企業では、年次を重ねたプログラマーはコスパが悪いと思われがちでした。
特にバブル崩壊後の不況期には、企業のITに対する投資が渋られるようになりました。
技術一筋のエンジニアが、30代後半になると「新人のほうが安く済む」ということで人事から肩を叩かれてしまうケースもあったと言います。このように歳を重ねたプログラマーたちが閑職に追いやられたり退職勧奨を受けたりする現象も、「35歳定年説」を裏付ける土壌となったかと思います。
過酷な長時間労働(いわゆる「デスマーチ」)
2000年代頃のSIerや下請けでは、企業や案件によっては連日の深夜残業や徹夜作業が常態化していました。納期直前には体力勝負の働き方を強いられるため、「有能でも体力の限界が先に来る」ような環境だったと言えます。
実際に優秀な開発者が30代半ばで燃え尽きてしまうようなケースも多く、「35歳で現場についていけなくなるのは能力より体力の問題」という実態もありました。
企業のキャリア制度と中途採用慣行
かつて日本の多くのIT企業では、エンジニアがエンジニアのまま定年まで勤め上げられるような制度が未整備で、優秀な人ほど途中で管理職や営業職にシフトせざるを得ませんでした。結果「35歳を過ぎてなおプレイヤーでいる人材」は社内で居場所がなくなりがちで、中途での転職も難易度は高いとされていました。
実際IPAによる2007年の調査では、40代を境にIT業界から他業種へ転職する人が急増し、IT業界からの流出組が全体の45%に達するという結果が出ていました。
上記のような理由から、かつては「ITエンジニア=35歳くらいまでの仕事」というイメージが定着していました。しかしもちろん、これらはあくまで当時の業界風土に起因する一面的な捉え方にすぎません。
ここからは、現在もなお35歳定年説に当てはまる状況が続いているのかどうかについて、データや近年の動向から検証します。
【参考】
「IT人材市場動向予備調査」(調査年:2007年度)
35歳を超えたエンジニアのキャリアと雇用状況
結論から言うと、「35歳定年説」はもはや過去のものとなっています。多くのITエンジニアが35歳をすぎても第一線で活躍し、業界全体の年齢構成も高齢化が進んでいます。
経済産業省の調査によると、2010年時点ではIT人材の約42%が34歳以下で、50歳以上は11%でしたが、2020年には50歳以上が22%まで増加しています。ここ10年でエンジニア層の高齢化が進み、中堅・シニア世代が大幅に増えたということです。
また厚生労働省によると、システムエンジニアの平均年齢は基盤系が41.8歳、組込み系が38.6歳、プロジェクトマネージャは41.8歳です。 エンジニアの平均年齢が40歳前後という現状は、「35歳で現場を去る人ばかりではない」どころか、多くのエンジニアがそれ以降もキャリアを積んでいる証です。
さらに、年齢とともにエンジニアの担う役割や雇用形態にも変化が見られます。
一般に20~30代の若手は「実務的な技術力とその成果」によって評価されますが、40代以降になると「マネジメント能力や豊富な経験」が評価されやすくなり、それに応じてポジションや給与も上昇する傾向があります。
少し前にはなりますが、経済産業省が調査したITエンジニアの職種別の平均年収を見ると最も高収入なのは40代が多いプロジェクトマネージャで約892万円、次いでITアーキテクトなど高度SEが約778万円と、管理職・高度専門職としてキャリアアップしたベテランほど高年収を得ています。
裏を返せば、適切なキャリアパスを積めば35歳を過ぎても収入も市場価値も向上し得るということです。企業側も近年は「シニアエンジニア=貴重な戦力」ととらえ、経験豊富な人材を厚遇する例も増えています。
一方でフリーランスや契約社員として活躍する道を選ぶ人も増え、柔軟な働き方が広がっています。フリーランス協会が公開した「フリーランス白書2023」によると、エンジニア・技術開発系フリーランスの8割以上は年収400万円以上で、会社員と比べても遜色ない収入を得ていることがわかります。
またシニア向け人材サービス「シニアジョブ」の調査では、シニアITエンジニア求人の56.2%が「定年なし」、66.3%が「再雇用年齢制限なし」と、年齢に関係なく長く働ける求人が過半数を占めていることもわかりました。
なお同調査ではシニア求人における約5割の契約形態が派遣(契約)社員でした。ただ、そのぶん「残業少なめ」「勤務日数相談可」といった柔軟な条件の求人も多く、定年後もスキルを活かしてほどよく働く選択肢が増えていることがわかります。
このように、現在のIT業界では35歳を超えてもエンジニアとして十分活躍でき、企業側も以前ほど年齢で線引きはしていません。むしろ少子高齢化とIT人材不足の深刻化により、今後はますますシニア層の力が求められると予想されます。経済産業省の推計では、2030年に向けてIT人材の平均年齢はさらに上昇を続けて高齢化が進むとともに、最大で約40万~80万人ものIT人材が不足する恐れもあるとされています。
ちなみにpaiza転職のように、35歳以上のエンジニアを対象とした求人情報を多数掲載している転職サービスも多数あります。転職やキャリアアップに興味のある方は検索してみるのもオススメです。
こうした需給ギャップを埋めるには、若手の育成だけでなく中高年エンジニアの活躍が不可欠となるでしょう。
【参考】
参考資料(IT人材育成の状況等について)
「jobtag」厚生労働省
IT関連産業の給与等に関する実態調査結果
フリーランス白書2023
ITエンジニアのシニア向け求人傾向調査、過半数が定年なし・再雇用上限なし【プレスリリース】|株式会社シニアジョブ
IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果
若手とベテランで異なるキャリアパスと待遇
もはや「35歳定年説」が崩れているとはいえ、若手とベテランではキャリアや働き方が異なるのは確かです。若いエンジニアは、最新技術の習得や実装で先頭に立つ「プレイヤー」としての比重が大きく、成果がダイレクトに評価されます。
対してキャリアを積んだエンジニアは、プロジェクトマネジメントやコンサルティング、後進の指導など「チームを率いる」「組織の価値を高める」役割を担う場面が多くなるでしょう。本人の志向や専門分野にもよりますが、結果として35歳前後で組織における役割がシフトするケースは少なくありません。
また最近は新卒から同じ企業に勤め続ける人ばかりでなく、30代でベンチャー企業に転職したり、独立してフリーランスになったりする人も珍しくありません。近年は中途採用市場が活発化し、35歳以上でも即戦力となるスキルがあればすぐに採用される場合もあります。
企業側も慢性的な人材不足を背景に年齢制限を緩和し、「経験10年以上のベテラン募集」「シニア歓迎」といった求人も増えています。35歳は、もはや転職市場でハードルとなる年齢ではないと言えるでしょう。
もっともベテランエンジニアのすべてが順風満帆というわけではありません。年次の割にスキルが未熟であれば、組織によってはポスト不足に陥る恐れもあります。
また家庭の事情やライフイベント(結婚・育児・介護など)によっては、30代以降での転職を躊躇したり現職に留まる選択をしたりする人もいます。このあたりは個人の状況によってキャリア戦略が左右されるでしょう。
重要なのは、年齢よりもスキルの陳腐化や環境適応力の欠如がキャリアを停滞させるということです。
最近は多くのエンジニアがオンライン学習やコミュニティ活動を通じて生涯学習に励み、年齢に関係なく新たな技術領域に挑戦しています。「情熱と向上心さえあれば、年齢は関係ない」ことは、今や業界の共通認識となっているのではないでしょうか。
まとめ:現在の「35歳定年説」の位置づけ
「ITエンジニア35歳定年説」は、かつては一定のリアリティを持った業界伝説でしたが、現代においてはほぼ神話化したと言ってよいでしょう。かつて長時間労働に明け暮れた世代も今や40・50代となり、依然エンジニアとして元気に活躍している人も少なくありません。むしろ彼らが牽引する形で、労働時間の短縮やリモートワークの普及などといった環境の改善が進み、35歳で体力的な限界を迎えるような説は過去のものとなりつつあります。現代のIT業界において、年齢だけで一律にキャリアの区切りを論じることは適切ではないでしょう。
ただ、当時の「35歳定年説」が無意味だったとは言い切れません。この説が提示していたのは、エンジニアが長期に活躍するために乗り越えるべき壁の存在でした。開発業務だけに安住せず、マネジメントスキルやビジネスに関する理解を深め、学習し続ける姿勢を保つことはエンジニアにとって重要な課題です。
今や35歳という年齢自体に特別な意味はありませんが、働き盛りの中間地点として、自らのキャリアを見つめ直す節目としてはよいタイミングなのかもしれません。
paiza転職では、ITエンジニア向けの求人情報を開発ジャンルや使用言語、給与額などだけでなく、一部在宅勤務可、原則定時退社、時短勤務可、イヤホンOK、裁量労働、副業OK、スキル研修が充実…などなど、さまざまな基準や条件で検索することができます。
またスキルチェック問題に挑戦すると、結果によってS・A・B・C・D・Eの6段階のランクを取得できます。ランクが上がれば上がるほど応募できる求人も増えるため、自分の市場価値を把握するのにも役立つでしょう。
すぐには転職を考えていない方でも、自分のプログラミングスキルを客観的に知ることが可能です。「自分のプログラミングスキルを客観的に知りたい」「スキルを使って転職したい」という方は、ぜひ挑戦してみてください。
【参考】
エンジニア就活コラム「SE35歳定年説の真実」
35歳定年説とは?エンジニアの定年が35歳と言われている理由
ITエンジニア35歳定年説のその後: 実際に達者でやってる人達のキャリア事例|久松剛

「paizaラーニング」では、未経験者でもブラウザさえあれば、今すぐプログラミングの基礎が動画で学べるレッスンを多数公開しております。
詳しくはこちら